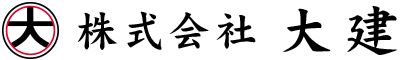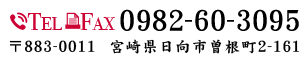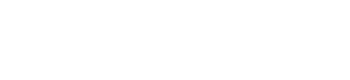宮崎県日向市を拠点に公共土木工事や道路工事、谷止工・土木治山などの型枠工事を手がける株式会社大建です。当社は宮崎県日向市を中心に延岡市など県内各地で活動しており、地域の安全と発展を支える工事に携わってきました。今回は、私たち道路工事のプロが「谷止工・土木治山」について詳しく解説します。近年、気候変動の影響で集中豪雨が増加し、土砂災害のリスクが高まっている宮崎県北部地域において、谷止工や土木治山工事がどのように地域の安全を守っているのか、その重要性と技術について紹介していきます。
谷止工と土木治山工事の基本知識

谷止工(たにどめこう)と土木治山工事は、山間部の災害防止に欠かせない工事です。特に宮崎県北部のような山地が多い地域では、これらの工事が地域の安全を守る重要な役割を担っています。
谷止工とは、山間の谷筋に設置する治山ダムのことで、土砂の流出を防ぎ、渓流の侵食を抑制する役割があります。一方、土木治山工事は、森林の維持・造成によって山地の崩壊を防ぎ、土砂災害を未然に防止するための工事全般を指します。
宮崎県は全国でも有数の多雨地域で、特に県北部の日向市や延岡市では年間降水量が多く、台風の影響も受けやすい地域です。そのため、谷止工や土木治山工事は地域の安全を守るための必須のインフラとなっています。これらの工事により、豪雨時の土砂流出を防ぎ、下流域の家屋や農地、道路などを保護することができるのです。
谷止工と土木治山工事の違い
谷止工と土木治山工事は密接に関連していますが、それぞれ目的や施工方法に違いがあります。谷止工は主に渓流に設置する構造物で、土砂の流出を物理的に防ぐことが主な目的です。一方、土木治山工事は植林や山腹工など、より広範囲の山地保全を目的とした工事を含みます。
谷止工は主に「渓流における土砂災害の防止」に特化していますが、土木治山工事は「山地全体の保全」を目的とする総合的な取り組みです。両者を適切に組み合わせることで、効果的な災害防止が実現できます。
宮崎県北部における谷止工の重要性
宮崎県北部、特に日向市や延岡市周辺は山地が多く、急峻な地形が特徴的です。この地域では、梅雨や台風シーズンになると短時間で大量の雨が降ることがあり、土砂災害のリスクが高まります。
実際に過去には、台風や集中豪雨により多くの土砂災害が発生しています。2005年の台風14号では宮崎県内に大きな被害をもたらし、特に県北部では土砂崩れや河川の氾濫が相次ぎました。その際、谷止工が設置されていた区域では被害が軽減されたという事例も多く報告されています。
谷止工は単に災害を防ぐだけでなく、土砂の流出を抑えることで森林の保全にも貢献しています。宮崎県北部の豊かな森林を守り、その恵みを持続的に享受するためにも、谷止工の設置と適切な維持管理が欠かせません。
日向市・延岡市における谷止工の施工実績
当社が施工に携わった日向市や延岡市の谷止工プロジェクトでは、地域の特性に合わせた設計と施工を行ってきました。特に耳川流域では、過去の災害経験を踏まえた効果的な谷止工の配置を行い、下流域の安全確保に貢献しています。
宮崎県の山地災害発生状況
年間平均発生件数:約40件(2015-2020年)
主な被害地域:県北部(延岡市、日向市、高千穂町など)
最近の大規模災害:2018年台風24号、2020年7月豪雨
谷止工の効果
土砂流出防止率:適切に設置された谷止工では約70〜80%
流木捕捉効果:約90%(コンクリート製スリット型)
経済効果:下流域での災害復旧費用の大幅削減
日向市・延岡市の地形特性
平均傾斜度:山間部で25度以上の急斜面多数
年間降水量:約2,500〜3,000mm(全国平均の約1.5倍)
地質特性:風化しやすい地質が多く、崩壊リスクが高い
谷止工の種類と特徴
谷止工には様々な種類があり、設置場所の地形や目的に応じて最適なタイプが選ばれます。宮崎県北部で多く見られる谷止工の種類と特徴について解説します。
最も一般的なのはコンクリート製の谷止工です。堅固で耐久性に優れ、大きな土砂流を食い止める力を持っています。特に延岡市や日向市の山間部では、台風や豪雨による大量の土砂流出に備えて、このタイプの谷止工が多く設置されています。
また、環境に配慮した自然石を活用した石積谷止工も、景観との調和が求められる場所では採用されています。日向市内の観光地に近い場所では、周囲の自然環境と調和した石積谷止工が設置され、防災機能と景観の両立を図っています。
最近では透過型(スリット型)の谷止工も増えてきています。これは普段は水や小さな土砂、魚などの生物を通過させながら、洪水時には流木や大きな岩石・土砂を捕捉するもので、生態系への影響を最小限に抑えつつ防災効果を発揮します。
各種谷止工の比較
谷止工の選定は、設置場所の特性や期待する機能によって異なります。ここでは、主な谷止工タイプの比較を示します。
コンクリート不透過型
特徴:強度が高く、大量の土砂を捕捉可能
耐用年数:約50〜100年
コスト:中〜高(規模による)
適した場所:土砂流出が激しい渓流、保全対象が近い場所
スリット型(透過型)
特徴:平常時は水や土砂を通し、洪水時に大きな土砂や流木を捕捉
耐用年数:約40〜80年
コスト:高(構造が複雑なため)
適した場所:生態系への配慮が必要な渓流、流木対策が必要な場所
石積み型
特徴:自然景観との調和が良い、透水性がある
耐用年数:約30〜50年
コスト:低〜中(材料と施工方法による)
適した場所:景観への配慮が必要な場所、土砂流出量が比較的少ない渓流
谷止工の選定では、「防災効果」だけでなく「環境への影響」「景観との調和」「維持管理のしやすさ」「コスト」など多角的な視点での検討が必要です。宮崎県北部の各地域の特性に応じた最適な谷止工を選定することが、効果的な災害防止には欠かせません。
土木治山工事の施工技術

土木治山工事には様々な施工技術が用いられます。宮崎県北部での実際の施工事例を踏まえながら、主要な技術について解説します。
山腹工は斜面の安定化を図る工法で、植生の回復と合わせて崩壊地を修復します。日向市の急斜面では、法枠工と植生工を組み合わせた工法が多く採用されています。これにより、斜面の安定化と緑化の両方が実現し、景観的にも自然に溶け込む仕上がりとなります。
渓間工は渓流沿いの浸食防止や土砂流出を抑制する工法です。谷止工や床固工などの構造物を設置して、渓流の侵食を防ぎ、流れを安定させます。延岡市の山間部では、渓流の特性に合わせた様々なタイプの渓間工が設置されています。
地すべり防止工は、大規模な地すべりが発生している、または発生する恐れがある箇所で実施される工法です。排水工事や杭打ち工など複数の工法を組み合わせて地すべりを抑制します。宮崎県北部の地すべり危険区域では、綿密な地質調査に基づいた効果的な地すべり防止工が実施されています。
宮崎県北部での施工上の課題と対策
宮崎県北部での土木治山工事には、いくつかの特有の課題があります。まず、急峻な地形が多いため、機械の搬入や作業の安全確保が難しい場所があります。当社では軽量機材の活用や、場合によっては人力施工も取り入れることで、こうした場所での施工を可能にしています。
また、多雨地域であるため、工事期間中の降雨対策も重要です。特に梅雨から台風シーズンにかけては、工程管理を慎重に行い、緊急時の安全対策を徹底しています。さらに、施工時期を冬季から春季に設定するなど、降雨リスクの低い時期に重要な工程を集中させる工夫も行っています。
山腹工の主な工法
法枠工:コンクリートや鋼製の枠を設置して斜面を安定化
植生工:種子吹付けや植栽による緑化
擁壁工:コンクリートや石積みで斜面を支持
宮崎県での特徴:在来種を活用した生態系に配慮した植生工の採用
地域特性に応じた工法選定
延岡市北川地区:流木対策を強化したスリット型谷止工
日向市東郷地区:景観に配慮した自然石活用工法
高千穂町周辺:急峻な地形に対応した軽量資材活用工法
日向灘沿岸部:塩害対策を施した高耐久性コンクリート使用
工事で使用される主な型枠技術
残存型枠:型枠を取り外さずそのまま残す工法
システム型枠:大型パネルを組み合わせて効率化
曲面型枠:自然な谷地形に合わせた型枠技術
技術習得期間:基本技術で3年、応用技術で5年以上
谷止工・土木治山工事の型枠施工技術
谷止工や土木治山工事において、型枠工事は構造物の品質を左右する重要な工程です。特に当社の専門分野である型枠工事について、その技術と特徴を解説します。
谷止工の型枠工事では、コンクリートが流れ出したり、形状が崩れたりしないよう、高精度な型枠の設置が求められます。さらに、現場は多くの場合急斜面に位置しているため、安全確保と正確な施工の両立が必要となります。
当社では長年の経験から培った型枠技術により、複雑な形状の谷止工でも精密な施工を実現しています。特に、スリット型谷止工のような複雑な形状では、専用の型枠システムを活用し、精度と効率の両立を図っています。
型枠工事の品質管理
品質の高い谷止工を実現するためには、型枠工事の品質管理が欠かせません。当社では以下のような点に特に注意して施工を行っています。
まず、型枠の強度計算を綿密に行い、コンクリート打設時の圧力に耐える構造を確保します。特に高さのある谷止工では下部の圧力が大きくなるため、補強材の配置などに細心の注意を払います。
また、型枠の組立精度も重要です。寸法誤差が生じると、完成後の谷止工の機能に影響を及ぼす可能性があります。当社では高精度な測量技術と熟練の技術者による施工で、高い精度を実現しています。
さらに、コンクリート打設時の型枠の変形防止も重要な管理ポイントです。コンクリートは液体状態で型枠内に流し込まれるため、打設速度の管理や適切な締め付け具の配置により、型枠の変形を防止しています。
型枠工事の手順
拾い出し:図面から必要な材料や寸法を拾い出す作業
加工:木材を切断して型枠を作成
墨出し:型枠を組み立てる位置の測量・マーキング
建て込み:型枠の組立・設置・固定
コンクリート打設:型枠内へのコンクリート投入
型枠工事の安全対策
転落防止:安全帯の使用、足場の設置
倒壊防止:支保工の適切な配置と固定
荷崩れ対策:材料の適切な積み方と固定
気象条件対応:強風・豪雨時の対策、避難基準の設定
型枠工事の精度管理
許容誤差:3mm以内(一般的な谷止工の場合)
使用測量機器:トータルステーション、レベル、レーザー墨出し器
品質チェック方法:第三者による計測確認、写真記録
耐用年数との関係:高精度施工で設計耐用年数を確保
型枠工事は谷止工の「見えない品質」を左右する重要な工程です。3mm以内という高精度な施工が求められ、これが構造物の耐久性や機能性に直結します。特に宮崎県北部の山間地では、地形の複雑さから更に高度な技術が必要とされます。
谷止工・土木治山工事の将来展望

近年の気候変動により、これまで以上に集中豪雨や台風の強大化が予測されており、谷止工や土木治山工事の重要性は一層高まっています。宮崎県北部地域の将来に向けた取り組みについて解説します。
まず、ICTやドローン技術の活用が進んでいます。地形測量や完成後の点検などにドローンを活用することで、人が立ち入りにくい場所でも正確なデータ取得が可能になっています。当社でも最新技術を積極的に導入し、より安全で効率的な施工を実現しています。
また、環境に配慮した工法の開発も進んでいます。生態系に配慮したスリット型谷止工や、周囲の景観と調和する自然石を活用した工法など、防災機能と環境保全の両立を図る取り組みが増えています。日向市や延岡市の豊かな自然環境を守りながら、安全を確保するためのバランスの取れた施工が求められています。
さらに、既存施設の老朽化対策も今後の課題です。過去に建設された谷止工や治山施設の中には、老朽化が進み機能低下が懸念されるものもあります。こうした施設の点検・診断技術の向上や、効率的な維持管理・更新技術の開発も進められています。
地域との協働による持続可能な取り組み
谷止工や土木治山工事は、単に施工して終わりではなく、地域との協働による維持管理や防災教育も重要です。日向市や延岡市では、地域住民を巻き込んだ防災訓練や、治山施設の点検活動なども行われています。
当社も地域の一員として、こうした活動に積極的に参加し、技術的な知見の提供や、安全な地域づくりへの貢献を行っています。施工者の視点からの説明や、施設の重要性の啓発活動なども、防災意識の向上に役立っています。
最新技術の導入状況
ICT施工:3次元測量、マシンガイダンス技術
ドローン活用:測量・点検・モニタリング
AR/VRの活用:施工シミュレーション、維持管理
宮崎県の導入率:ICT施工の導入率約40%(2024年時点)
環境配慮型工法の普及状況
生態系配慮型谷止工:宮崎県北部での採用率約35%
自然素材活用:間伐材や地域産石材の活用増加
緑化技術:在来種による早期緑化、生態系復元技術
効果事例:耳川流域での魚類生息環境改善事例
今後の整備計画
宮崎県北部計画:5年間で約50箇所の谷止工新設・改修
重点整備地域:日向市東郷地区、延岡市北川地区
事業費見込み:約30億円(県・国事業合計)
技術者需要:施工管理技術者・型枠技術者の需要増加
災害事例から学ぶ谷止工の効果
過去の災害事例から、谷止工がどのように効果を発揮したかを見ることで、その重要性がより明確になります。宮崎県北部で実際に起きた災害事例と、谷止工の効果について紹介します。
2018年に宮崎県北部を襲った台風24号では、各地で土砂災害が発生しました。しかし、谷止工が適切に設置されていた区域では、下流への土砂流出が抑制され、被害が最小限に抑えられた事例があります。特に日向市の山間部では、複数の谷止工が土砂や流木を捕捉し、下流域の集落を守りました。
また、2020年7月の豪雨では、延岡市北川町周辺で多くの斜面崩壊が発生しましたが、治山事業が実施されていた箇所では、崩壊規模が小さく抑えられ、迅速な復旧が可能となりました。
一方で、谷止工が未整備であった地域では大きな被害が発生した事例もあります。このような対比から、谷止工の整備がいかに重要であるか、具体的に理解することができます。
効果的な谷止工配置の考え方
谷止工の効果を最大化するためには、適切な配置計画が重要です。特に宮崎県北部のような急峻な地形では、単一の谷止工ではなく、複数の谷止工を階段状に配置する「階段谷止工」が効果的です。
また、谷の状況や保全対象との距離、地質条件なども考慮し、最適な配置と構造を選定する必要があります。当社では長年の経験から、地域の特性に合わせた最適な谷止工配置を提案し、効果的な防災対策に貢献しています。
2018年台風24号の事例
被災地域:日向市東郷町、美々津地区
降雨量:24時間雨量約400mm
谷止工効果:約1,500m³の土砂と流木を捕捉
被害軽減効果:下流集落の床上浸水被害回避
2020年7月豪雨の事例
被災地域:延岡市北川町、北方町
降雨量:48時間雨量約600mm
治山工事効果:複数の斜面崩壊が小規模で抑制
経済効果:復旧工事費約2億円の節減効果
谷止工の費用対効果
建設費用:中規模コンクリート谷止工で約5,000万円
維持管理費:年間コストの約2%程度
期待寿命:適切な管理で80〜100年
防災効果:下流域で10〜20倍の復旧費用節減効果
谷止工の効果は実際の災害事例から明らかです。適切に設置された谷止工は、土砂災害による被害を大幅に軽減し、人命や財産を守ります。特に宮崎県北部のような多雨地域では、計画的な谷止工の整備が地域の安全を守る鍵となっています。
まとめ:谷止工・土木治山工事の地域を守る力
この記事では、宮崎県北部における谷止工・土木治山工事の重要性と、その施工技術について解説してきました。これらの工事は、日向市や延岡市をはじめとする宮崎県北部の山間地域の安全を守る重要なインフラであり、豪雨や台風による災害から人命や財産を守る役割を担っています。
特に近年の気候変動による豪雨の増加や台風の強大化に伴い、これらの防災施設の重要性は一層高まっています。過去の災害事例からも、谷止工や治山工事の効果は明らかであり、適切に整備された地域と未整備の地域では、被害の程度に大きな差が生じています。
当社(株式会社大建)は、日向市を拠点に長年にわたり公共土木工事や谷止工・土木治山などの型枠工事に携わってきました。培ってきた技術と経験を活かし、これからも宮崎県北部地域の安全・安心な暮らしを支える工事に取り組んでいきます。安全で美しい郷土を次世代に引き継ぐため、最新技術の導入や環境に配慮した工法の採用など、常に進化し続ける施工技術で地域の防災に貢献していきます。